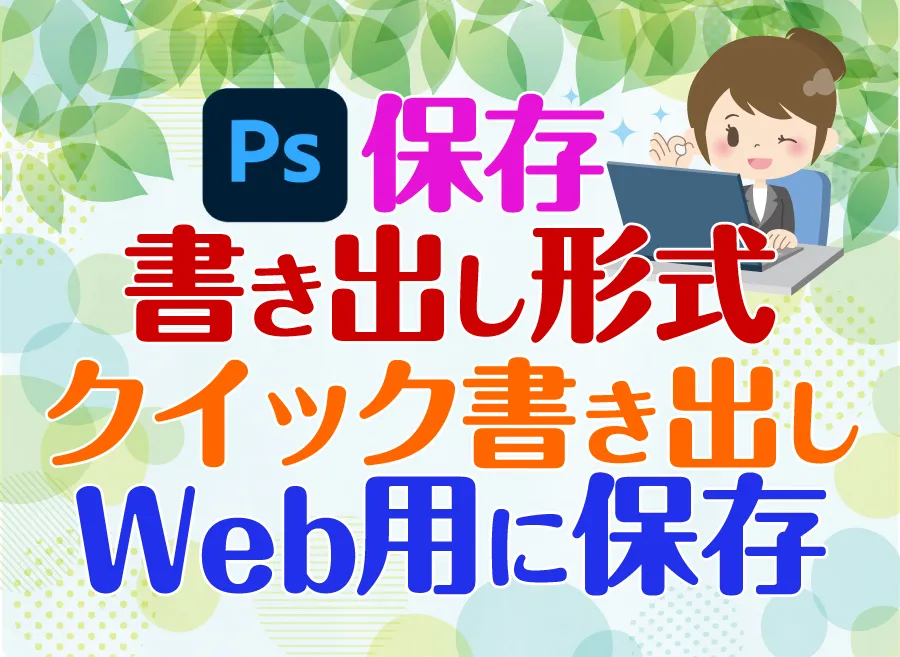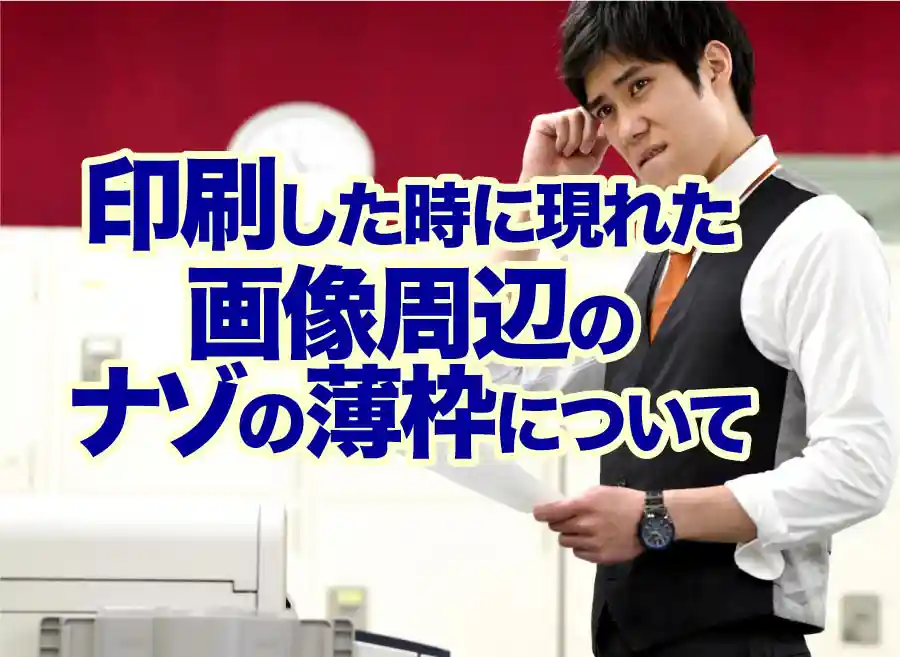「出版社」が東京一極集中になる原因は?

DTP(Desktop Publishing)の登場でデザインのデジタル化が進み、デザイナーや編集者はノートPC一つあれば、どこでも作業できることは常識ですが、「出版社」は7割以上が今もなお東京に集中している、という話は本当でしょうか?
また、出版業界でよく聞く「取次(とりつぎ)」とは、一体何をしているところでしょう?
2025年現在、書店数の減少や「物流クライシス」といった新しい課題も出てきています。こうした背景も踏まえながら、出版業界が持つ独特の仕組みを見ていきます。
数字で見る「東京一極集中」のリアル
結論から言うと、「出版社の7割以上が東京に集中」という状況は、2025年になっても変わっていません。最終的な「モノ」としての本を動かす「流通」の仕組みは依然、東京が中心地です。
業界の今を、いくつかの数字で見てみましょう。
出版社数は?
日本全国に約4,000社(参考サイト:政府統計の総合窓口(e-Stat)※統計により変動あり)あるとされますが、名前の知られた大手出版社の多くは東京(特に千代田区・新宿区など)に集まっています。
書店数は?
ここが最も大きな変化です。 かつて(2010年代)は約16,000店ありましたが、2025年の調査では約10,250店(参考サイト:BookLink・他、文化通信 2025年9月4日配信)と、かなり少なくなっています。
アイテム数は?
定期雑誌だけでも約3,000誌(参考サイト:出版科学研究所・他PDF ※休刊も相次ぎ流動的)あり、さらに毎日たくさんの新刊(単行本・コミックなど)が発行されています。
これだけ多くの種類の本を全国の書店(減ったとはいえ1万店以上!)に届けるには、とても特殊な流通システムが必要になります。
出版流通の心臓部「取次(とりつぎ)」とは?
ここで、他の印刷物と比較してみましょう。 例えば「新聞」であれば、速報性が命なので、全国各地にある印刷所で生産(印刷)し、そこからすぐに配達するという流れが一般的です。
しかし、「雑誌や単行本などの書籍」は異なります。 生産のほとんどが東京近郊の印刷所でまとめて行われます。なぜなら、その方が印刷コストを安く抑えられるからです。
そして、刷り上がった本は、印刷工場から全国の書店に直接送られるわけではありません。 原則として、いったん「取次(出版販売会社)」の巨大な物流センターに集められる流れになっています。
「取次(とりつぎ)」は、一言でいえば「本の大きな問屋さん」。 全国の出版社から集めた多種多様な本を仕分けし、全国約1万店の書店に送り届ける役割を担っています。
そして、この取次業界は「日本出版販売(日販)」と「トーハン」という大手2社が大きなシェアを持っており、両社とも東京に本社と巨大な拠点を持っています。
出版社が東京に集まる大きな理由のひとつは、この「取次」が東京に大きな拠点を持っているから、というわけです。
▲ YouTube 引用:【三機工業】納入事例「トーハン様 和光センター|新刊発送ラインコンベヤ|輸送方面別仕分けソータ」
なぜ「取次」を経由する必要があるのか?
では、なぜ出版社はAmazonや他の物流会社を使わず、取次を経由するのでしょう?背景には、日本の出版文化を支えるための大切な役割があります。
1. 全国どこでも同じ価格の「再販制度」
日本の本や雑誌は、基本的に全国どこの書店で買っても同じ価格(定価)ですよね。これは「再販売価格維持制度(再販制度)」というルールで、定価販売が決められているからです。
これは「どこに住んでいても、公平に本と出会えるように」という文化的な側面を大切にしているためです。取次は、この仕組みを全国規模で運用・管理する役割を担っています。
2. 雑誌の「全国同時発売」の実現
雑誌は、基本的に「同じ地区なら同じ発売日」が守られています。これも、取次が全国の物流を調整してくれているからこそ実現できています。
【最大の変化】物流クライシス(危機)「2024年問題」の直撃
かつて、この「取次」を中心とした流通網は、「共同配送」などで効率化が図られていましたが、2025年現在、この状況が大きく変わってしまいました。物流業界全体が直面している「2024年問題(トラックドライバー不足や残業規制による輸送力ダウン)」が、本の世界にも大きな影響を与えているのです。
▲ YouTube 引用:FULL「知ってる?トラック輸送の“今”~物流の2024年問題を考えよう~」
物流クライシスとは、モノを運ぶ仕組み(物流)がうまく回らなくなる大ピンチ、という状況のこと。
ネット通販(EC)の急増 で運ぶモノの「個数」が昔より爆発的に増えているのに、トラックドライバーの不足や、2024年から始まった「残業規制(働く時間の上限)」によって、今まで通りにモノを運べなくなる深刻な問題です。 送料の値上げや、配送の遅れといった形で、私たちの生活にも影響が出始めています。
運送コストがどんどん高く…
この物流クライシスにより、運賃自体が記録的に高騰しています。このコスト増は、取次会社や出版社の経営にとって、かなりの負担となっています。
「日本出版取次協会」の試算では、国の示す「標準的な運賃」を適用すると、業界全体の物流コストが倍増(約300億円の負担増)する可能性も示唆されています。
値上げが難しいジレンマ
物流コストが上がっても、「再販制度」があるため、すぐに本の定価に上乗せすることができません。
もはや「効率化」どころか、「遠くの書店へ、どうやって採算を合わせながら本を届け続けるか(物流網を守るか)」という、とても難しい課題に直面しているのが実情です。
「書店数の激減」と「物流の危機」で取次と流通の仕組みはどうなる?
本の「制作(DTP)」はデジタル化して場所を選ばなくなりましたが、「流通(物流)」がこれまでの仕組み(取次システム)に支えられている限り、出版社の東京一極集中は簡単には変わらないでしょう。
けれども、その大切な「流通」の仕組み自体が、
-
書店数の激減(モノを届ける先の減少)
-
物流クライシス(モノを運ぶ手段の危機)
という2つの大きな課題によって、今まさに揺らいでいます。
「取次」のあり方が根本から変わる可能性は?

物流業界全体の動きから推察すると、未来は「効率化の徹底」と「モノ(紙)を運ばない選択」の二極化に進むと考えられます。
推察1「運ぶコスト」の上昇で「配送の仕組み」が変わる
物流クライシス(2024年問題)の本質は、ドライバー不足による「人件費の高騰」と「輸送力そのものの低下」です。これにより、これまで維持されてきた、きめ細やかな配送が困難になります。
-
「毎日配送」の終焉
全国の書店に毎日(あるいは頻繁に)本を届けるというサービスは、コスト的に維持できなくなるでしょう。地域によっては「週2回配送」など、配送頻度を落とさざるを得ない地域が出てくる可能性が高いです。 -
「雑誌の同時発売」の崩壊
配送頻度が落ちれば、全国一斉の「雑誌同時発売」という原則も維持が難しくなります。都市部は発売日通りでも、地方は1〜2日遅れるのが当たり前になるかもしれません。 -
物流の「共同化」から「最適化」へ
これまでは「出版業界」で共同配送を行ってきました。今後は、業界の垣根を超え、例えば「コンビニ配送網」や「地域の宅配業者の余剰スペース」など、すでにあるインフラに「相乗り」させてもらう形での最適化が進む可能性があります。
推察2「取次」の役割の変化(問屋から物流倉庫へ)
届ける先である「書店」が減り続けるため、「取次」の「問屋」としての機能(BtoB)は縮小せざるを得ません。
-
「BtoC(個人向けEC)」物流の強化
取次会社は、自らが持つ巨大な物流センターの機能を活かし、出版社から物流業務を受託する「倉庫業(フルフィルメントサービス)」や、読者個人に直接届ける「EC(ネット通販)」部門をさらに強化していくと考えられます。 -
「仕分け」から「データ管理」へ
物理的な本の仕分け作業は減る一方で、「どの本がどこで売れているか」「どこに需要があるか」といった膨大な販売データをAIで分析し、出版社にフィードバックする「データカンパニー」としての側面が強まる可能性があります。
推察3「モノを運ばない」仕組みの台頭
最も大きな変化は、「物流コストが高くなりすぎるなら、物理的に運ぶのをやめよう」という動きです。
-
プリント・オン・デマンド(POD)の普及
物流の観点から最も効率的なのは、「データを送り、消費地(またはその近く)で印刷する」ことです。 今まではコストが高かったPOD(注文を受けてから1冊ずつ印刷・製本する技術)も、物流費の高騰によって相対的に現実味を帯びてきます。 未来の書店は、店頭で見本誌を見て、気に入ればその場でPOD機で印刷・購入する…といった形になるかもしれません。 -
電子書籍への更なるシフト
物流問題は、皮肉なことに「紙の本」のコストを押し上げます。その結果、物流コストが一切かからない「電子書籍」への移行を、出版社も読者も選択する動機がより一層強まります。
まとめ:未来の出版流通
これまでの「取次が全国の書店へ一律に紙の本を届ける」という仕組みは、残念ながら維持が困難になっていくでしょう。
物流の動きから推察すると、今後は「都市部の大型書店・EC向け」と「地方・小規模書店向け」で、流通の仕組みが分かれていく可能性があります。
-
都市部・EC
巨大な物流拠点で自動化を進め、コストを抑えながら紙の本を配送。 -
地方・小規模
配送頻度を落とすか、あるいはPODや電子書籍での対応が中心となる。
「東京一極集中」自体は、大手出版社や取次本社があるためすぐには変わりませんが、PODやEC直販(出版社から読者へ直接配送)が普及すれば、その「集中」の意味合いは少しずつ薄れていくかもしれません。
2025年の出版業界は、「東京一極集中」というこれまでの形が、良くも悪くも変わり始める…そんな大きな転換点にいるのかもしれません。
【あわせて読みたいページ】