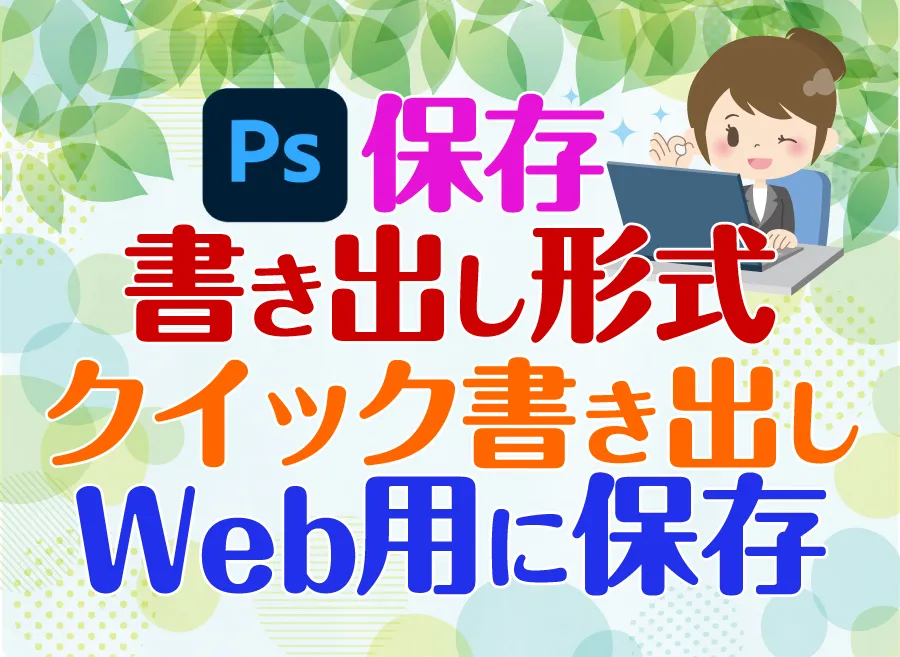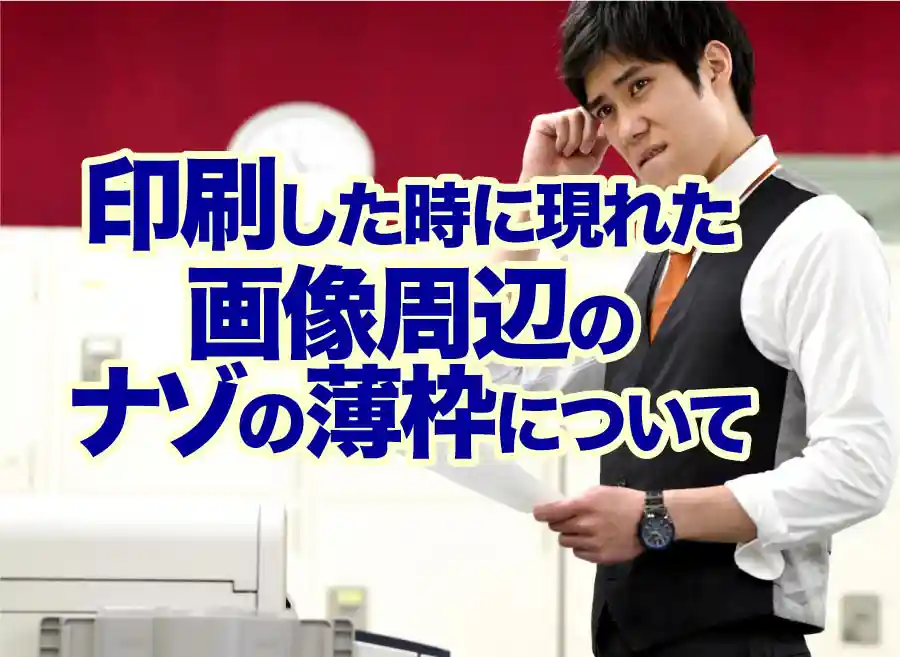前回の記事 【 印刷物が仕上がるまでの工程は? - vol.1 】では「面受け」や「トンボ」の役割などを交えて「紙面上の構成」について整理しました。
今回は「構成した紙面」を大量に複製するための工程について解説いたします。
この記事の目次
【 プリントアウト 】と【 プレス 】の違いは?
印刷の技法には「プリントアウト」と「プレス」の 2種類があります。
日本語では単純に印刷、もしくはプリントといいますが、これらの技法は印刷における概念が完全に別物です。
- プリントアウト (Printout)は、ご家庭にあるプリンタや、オフィスやコンビニにあるコピー機などの複合機に「データを出力」→「インプットして」→「紙に刷る」というものです。「プリンタ」や「コピー機」はデータを出力するという特質から「出力機 」とも呼ばれます。
- プレス (Press)は、印刷会社の大型の印刷機を指し、大量の紙や他の素材に高速でインキを転写する装置です。印刷機の「版胴(はんどう)という筒に版を巻き付け」→「インキを付けて」→「紙に転写」という流れの技法で「プレス( 押す・圧力をかける)」は商業印刷の主流です。
【プレス】の主流は「平版」を使った【オフセット印刷】
プレスでは印鑑や版画と同じ原理の「ハンコ」を使います。
そのハンコとなる版は「平版(へいはん)」・「凸版(とっぱん)」・「凹版(おうはん)」・「孔版(こうはん)」の4版式がある中でプレスの主流は「平版」で、他の3版式(凹凸を利用したハンコ)とは形状が異なる”水と油の反発性”を利用した印刷方式です。
「平版印刷」の一種で代表的な「オフセット印刷」は、コスト安で仕上がりが美しく長年チラシや出版物などのほとんどで使われています。
▲ 引用:YouTube【工場見学】全部見せます、印刷の現場〜オフセット印刷〜
「平版/オフセット印刷」徹底解説
- 平版は「平面 」の版で直接紙には触れず、1度ゴムローラー上に写し取り、そこから印刷します。
- 水と油の相反する性質を利用して、平らな原版(平版)の上に「親油面(油性の画像部→画像のある場所)」と「親水面(非油性の非画像部→画像の無い場所)」を作り「湿(しめ)し水」と「油性インキ」を供給しながら印刷します。印刷中の版は常に「湿し水」に濡れた状態で「親水性」部分は油性インキをはじきます。
※「湿し水」とは、非画像部に印刷インキが付着しないように版の非画像部を湿らせる液体のことです。 - オフセット印刷では平版を1度、中間転写体の「ブランケット版」というゴム版ローラーにインキを移して紙に刷り出すため、版面は「 正像 」です。(平版は間接的に紙に版を当てますが、他の3版式は凸凹(デコボコ)形状で直接、版を当てるため、版は「逆像(鏡像)」です。)
- この時、画像部のみにインキが付着するため、このインキを一度{ブランケット版に転写(→OFF→オフ)}してから、{紙に転写印刷(→SET→セット)}することから、オフセットと呼ばれています。
- 平版は、印刷機の「版胴(はんどう)」という筒に巻き付けセットしますが、版を個定するために{版胴の切れ目}である「クワエ」に端の数センチを食い込ませるので、この部分には画像を置かないようにします。
【 プレスの版式 】凸版・凹版・孔版とは?
「凸版(とっぱん)」とは
インキの付く部分を突き出させて、インキを付けない部分をヘコませた形式です。高低差を利用して突き出た部分にインキを付け、印刷物に圧力を加えて転写します。
新聞・雑誌の「輪転印刷」、書籍の「平台印刷」、美術品の「原色版印刷」、段ボールや紙袋の「フレキソ印刷」など幅広く活用され、鮮明で歪みが少ないことが特徴です。歴史上1番古い版です。
「凹版(おうはん)」とは
凸版の逆で、凹んだ部分にインキを詰めて、印刷物に転写して印刷する形式です。
美術や写真などの「芸術的な印刷」に適し代表的なものでは「グラビア印刷」があります。
粗さが目立たず複雑で味わいのある調子が出るので仕上がりが大変美しいです。
「孔版(こうはん)」とは
大小の細かい孔 (あな) をあけて、その孔からインキをにじみ出させて印刷する形式です。
インキの乾燥が遅く大量印刷に不向きなため一般商業印刷では、ほとんど使われませんが、平板や凹版では不可能な「湾曲した面の印刷」などの特殊な印刷や「軽印刷」の分野で多用されます。
外に「特殊加工の原紙」や、金属箔などを使った「謄写(とうしゃ)版印刷」、絹布の「(シルク)スクリーン印刷」などがあります。
「網点(スクリーン)」網掛け・平網・スミアミとは?
版を使って大量印刷する印刷インキでは、絵の具で絵を描くように「色を混ぜて塗る」なんてことはしません。
「モノクロ印刷」であればインキは黒1色で済みますが「灰色」を表現する場合、黒1色でどう表現するか?この疑問に答える形で版の特徴を解説します。
- プレスにおける「色の階調表現」は網点がすべてです。版に{細かい点}を格子状に並べた「網点(あみてん/英語でスクリーン)」を作り擬似的に色を表します。
- 網点の1つ1つの点は 真っ黒ですが目立たないよう(普通は)45度に傾けて並べます。色の濃度はパー セントで指定しますが、離れて見ると「灰色」に見えるのです。
- 「グラデーション」は網点がまったくない状態から、完全に塗りつぶした「ベタ」という状態まで、網点の大きさを少しずつ変えて並べることで濃度を調整し濃淡を表現します。
- DTP全般でこれら「色の階調表現」のことを「網掛け(あみがけ)」・「平網(ひらあみ)」・「スミアミ」といいます。一般で言う「灰色」や「グレー」という表現はしません。
「フルカラー印刷」のカラーモード「 CMYK」とは?
 「フルカラー印刷」の場合も「モノクロ印刷」と同様に色は「網点(あみてん/スクリーン)」で表現します。
「フルカラー印刷」の場合も「モノクロ印刷」と同様に色は「網点(あみてん/スクリーン)」で表現します。
「プロセスカラー」と呼ばれる C(シアン:藍)、M(マゼンタ:紅)、Y ( イエロー:黄)、K(ブラック:墨)の4色のインキをそれぞれ4版に分けて”掛け合わせ”て刷り上げます。
「掛け合わせ」とは多色印刷で2色以上のインキを重ね合わせて色を表現することです。
例えば、
M100% × Y100% の{網点}の 掛け合わせ = 赤(「キンアカ」と呼ばれる代表的な赤)
C100% × Y100% の{網点}の 掛け合わせ = 緑
といった具合に色を表現します。
K100%=黒は{色の三原色}の理論上、C・M・Y の3色の掛け合わせで表せるので本来3色の混インキ合で刷ると良さそうですが、実際は印刷の物理的な制約や利便性から「黒インキ」を使うことでくっきり美しい印象に仕上げています。
4版の網点を傾けて「モアレ模様」を回避する
4版(C版/M版/Y版/K版)それぞれの網点は、すべての版を同じ方向で重ねると色がつぶれて汚くなるので版ごとに角度を変えます。
角度は目分量で変えると「干渉縞(かんしょうしま)」と呼ばれる「モアレ(フラン ス語)状の模様」が発生し原理的にモアレを完璧に無くすことはできませんが、もっとも目立たない角度の組合せは経験的に確立されています。
この「網点(スクリーン)」の角度を「スクリーン角度」と呼び、CMKの中でモアレがめだつ1色を45度に置いて、他の版をそれぞれ30度ずつ傾け、モアレがめだたない薄い色のY版をいずれか2色の中間に置くことでモアレを回避します。
詳細はウィキペディア「モアレ」を参照ください。
印刷会社へ出稿した後はどうなってるの?【 印刷物が仕上がるまでの工程は? - vol.3 】へ 続く…(現在編集中)
【あわせて読みたいページ】